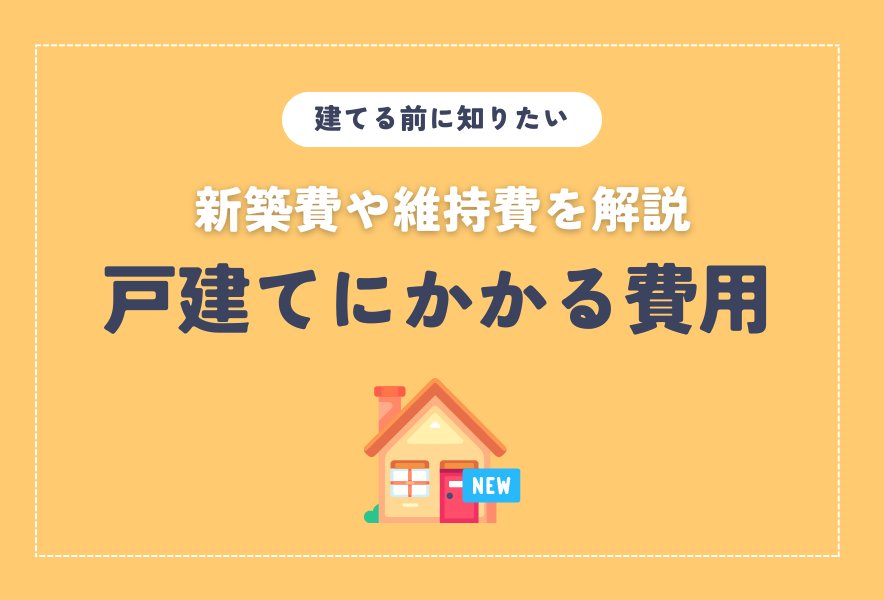新築で一戸建てを検討している方は、どのような費用がいくらかかるのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。本記事では、一戸建てを建てる際にどのような費用が発生するのか、維持費も含めて費用項目を整理し解説しています。
新築一戸建てにかかる費用

一戸建てを新築する際に発生する費用は大きく分けて3つあります。
費用項目別に、その内容を見ていきましょう。
- 建築費(本体工事費+付帯工事費)
- 土地代
- 諸費用(上記以外のその他必要な費用)
注文住宅の費用内訳(全国平均)
| 費用項目 | 割合 | ||
| 建築工事費 | 本体工事費 | 3,011万円 (68%) | 約70% |
| 付帯工事費 | 約20% | ||
| 諸費用 | 約10% | ||
| 土地代 | 1,445万円 (32%) | - | |
(HOME4Uまとめ:https://house.home4u.jp/contents/budget-2-105)
建築費の主な費用項目(本体工事費+付帯工事費)

一戸建て建築費は、大きく本体工事費と付帯工事費の2つに分けられます。本体工事費とは、建物の建築に直接かかわる費用のことで、主な工事費用項目は以下の通りです。
本体工事費
①基礎工事
基礎工事とは、建物を支える土台を作る工事のことです。地盤の強度に応じて工法が選ばれます。基礎工事には、地面を掘る掘削作業、コンクリートを流し込むコンクリート打設、鉄筋を組み込む鉄筋工事などが含まれます。
地盤が弱い場合は、追加で地盤改良工事が必要になり、費用が高くなることがあります。基礎がしっかりしていないと、建物の耐久性や安全性に大きく影響するため、非常に重要な工程になります。
②躯体工事(構造工事)
躯体工事とは、建物の骨組みを作る工事のことです。木造や鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの構造によって異なります。
木造の場合は土台敷き、柱・梁の組み立て、屋根の骨組みなどを行い、鉄骨造・RC造の場合は鉄骨の組み立てや型枠工事、コンクリート打設が含まれます。
建物の強度や耐震性に直結する重要な工事であり、構造計算に基づいて緻密に設計・施工されます。
③屋根・外壁工事
屋根・外壁工事は、建物の外観を形成し、雨風から守るための工事になります。屋根は瓦屋根、スレート屋根、金属屋根などの種類があり、断熱性や耐久性、デザインに影響します。
外壁にはサイディングやモルタル、タイルなどがあり、それぞれコストやメンテナンス性が異なります。外壁と屋根の間には防水シート(ルーフィング)を施工し、雨漏りを防ぐ処理も行われ、屋根工事同様に、耐久性やデザイン性を考慮した素材選びが重要となります。
④内装工事
内装工事は、建物の内部の仕上げを行う工事のことです。主な作業には、床の施工(フローリング・タイル・カーペット)、壁や天井の仕上げ(クロス貼り・塗装)、建具(ドア・クローゼット・収納棚)の設置などがあります。
断熱材の施工も含まれており、生活者の居住性を向上させる役割を果たしています。間取りに応じた造作工事(造作家具やニッチの設置など)も行われ、デザイン性だけでなく、耐久性やメンテナンスのしやすさも考慮する必要がある工事になります。
⑤設備工事(電気・通信・水道・ガス)
設備工事は、生活に必要なインフラを整備する工事です。
電気設備工事は、配線・コンセント・照明・インターネット回線などを設置する工事。水道工事は、給排水管の敷設、キッチン・浴室・トイレなどの水回り設備を設置する工事。ガス工事は、ガス管の引き込みや給湯器を設置する工事です。
各設備の配置は間取りと密接に関係し、使いやすさやメンテナンスのしやすさを考慮した計画が必要になります。
⑥断熱・気密工事
断熱工事とは、住宅の快適性と省エネ性を向上させるための工事のことです。断熱材(グラスウール・吹付ウレタン・発泡スチロールなど)を壁・天井・床下に施工し、室内の温度変化を抑えることができます。
サッシや玄関ドアには気密パッキンなどを使用し、隙間風を防ぎます。断熱・気密性能が低いと、冷暖房効率が悪化し、光熱費が高くなるため、高性能な断熱材や窓を採用することで快適な住環境を実現することができます。
付帯工事費
①地盤調査・地盤改良工事
地盤調査・地盤改良工事は、建築前に地盤の強度を調査し、必要に応じて地盤を補強する工事のことです。
地盤調査では、サウンディング試験やボーリング調査を実施し、地盤の支持力を確認します。軟弱地盤の場合は、表層改良(地盤を固める)、柱状改良(セメントの柱を埋める)、鋼管杭工事(鉄杭を打ち込む)などの補強工事が必要になります。地盤が弱いと、建物が沈下する恐れがあるため、適切な処置が必要不可欠になります。
②解体工事
解体工事は、既存の建物を取り壊して更地にするための工事のことです。
木造・鉄骨造・RC造など建物の構造によって解体方法が異なり、費用も変動します。万が一、アスベストが使用されている建物の場合は、専門業者による処理が必要となり、追加費用が発生することがあります。
解体後に地中障害物が見つかることがあり、その撤去費用がかかることもあるため注意が必要です。
③仮設工事
仮設工事は、あまりなじみのない工事名ですが、建築作業を安全かつ円滑に進めるための一時的な設備や施設を設置する工事のことです。
主に、足場の設置、仮設トイレの設置、資材置き場の確保、防塵・防音シートの設置などが含まれます。これらは工事完了後に撤去されるため、直接建物の仕上がりには影響しませんが、安全性や作業効率を左右するため、必要不可欠な工事になります。
④外構工事(エクステリア工事)
外構工事は、建物周辺の環境を整備する工事のことです。
駐車場の舗装、門扉・フェンスの設置、庭の造成、ウッドデッキの設置、アプローチやカーポートの施工などが含まれます。外構は住宅のデザインを決定づける要素の一つであり、防犯性やプライバシー確保、使い勝手を考慮することが重要です。コンクリートや天然石などの素材選びによって、工事費用が大きく変動します。
⑤防蟻・防湿工事
防蟻・防湿工事は、建物をシロアリ被害や湿気による劣化から守るための工事のことです。
特に木造住宅では、基礎部分や床下に防蟻剤を散布し、シロアリの侵入を防ぎます。また、湿気対策として、防湿シートを施工し、床下の結露を防ぐ処置も行われます。防蟻処理については、5~10年ごとに再施工が推奨されており、定期的なメンテナンス計画も必要になります。
⑥水道・ガス・電気の引き込み工事
インフラの引き込み工事は、新築する土地に水道・ガス・電気を供給するための工事のことです。
既存の配管・配線がない場合、新たに本管から敷地内へ引き込む必要があります。特に、水道は自治体ごとに水道加入金が必要となる場合があります。
ガスは都市ガスとプロパンガスで配管工事の内容が異なり、オール電化を選択するとガスの引き込みが不要になります。これらの工事はライフラインの基盤となるため、早めの手配が必要になります。
土地代の主な費用項目

土地代は、住宅を建築する土地を購入する際に発生する費用です。土地代には、単純な購入費用だけでなく、契約や税金、手続きに関連する費用が含まれます。
①土地購入費用(売買代金)
土地の本体価格で、不動産市場の相場や立地条件、土地の広さ、形状、周辺環境によって変動します。都市部では価格が高く、地方では比較的安価になる傾向があります。さらに、用途地域(住宅地・商業地など)や建ぺい率・容積率の制限によって、土地の利用可能性が異なります。希望する建物が建築できるかを事前に確認することが重要です。
②仲介手数料
不動産会社を通じて土地を購入する場合に発生する手数料のことです。宅地建物取引業法に基づき、上限が「土地代金の3%+6万円(税別)」と定められています。売主が不動産会社である場合は仲介手数料が不要となるケースもあります。手数料は契約成立時に支払うため、事前に確認し、予算に含めておきましょう。
③印紙税
土地の売買契約書に貼付する印紙代で、契約金額に応じた税額が決められています。例えば、契約金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合、印紙税は1万円(軽減措置適用時)となります。印紙税は契約書の正本・副本それぞれに必要となる場合があるため、契約時にはしっかり確認しておくことが必要です。
④登記費用(所有権移転登記)
土地の所有権を買主に移すための登記手続きにかかる費用です。法務局で手続きが必要で、一般的には司法書士に依頼することになります。費用は土地の評価額に応じた登録免許税と、司法書士への報酬が含まれます。登記を適切に行わないと所有権が正式に移転しないため、購入時には必ず手続きを行う必要があります。
⑤固定資産税・都市計画税
土地を所有することで発生する税金です。固定資産税は「土地の課税評価額×1.4%(標準税率)」で算出され、都市計画税は「土地の課税評価額×0.3%(上限)」が課税されます。購入した年の固定資産税は、売主と日割り計算により清算する場合が多いため、引渡し時に負担する額を事前確認することが重要です。
⑥水道負担金(加入金)
新しく水道を利用する際に自治体へ支払う費用です。土地に既存の水道管がない場合、新規に本管から引き込む工事が必要となり、加入金として10万円~30万円程度がかかることがあります。
⑦不動産取得税
土地を購入すると課税される地方税で、取得した不動産の固定資産税評価額に対して3%の軽減税率*が適用されます。住宅用地として購入した場合、課税標準が1/2になる特例が適用されることが多いため、事前に確認しておきましょう。(*令和9年3月31日までに「住宅」として取得した建物に対して3%の軽減税率が適用されます)
諸費用の主な費用項目(その他必要な費用)

①住宅ローン関連費用
住宅ローンを利用する際に発生する費用です。融資手数料(金融機関に支払う手数料)、保証料(保証会社を利用する場合に必要)、団体信用生命保険(団信、住宅ローン契約者が死亡・高度障害になった際にローン残債がゼロになる保険)、住宅ローン契約書などに貼付する印紙代などがあります。これらの費用は金融機関やローン商品によって異なるため、比較検討が必要です。
②火災保険・地震保険
火災保険や地震保険は、金融機関の住宅ローンを利用する場合は加入が義務付けられることが一般的です。火災保険は、火災や風水害に備える保険で、補償範囲や建物の構造によって保険料が変動します。地震保険は、地震による損害を補償する保険です。保険料は補償内容によりますので、補償内容と合わせて確認してください。
③建物の確認申請費用
建築基準法に基づき、建築確認申請を行う際にかかる費用です。自治体または指定確認検査機関に申請し、建築が法令に適合しているかを確認してもらいます。申請費用は建物の規模や申請先によって異なります。適合証明書の発行が必要な場合は、追加費用が発生することもあります。
④引越し費用
新居への移転にかかる費用です。移動距離や荷物量によって異なります。引越しに伴い、エアコンの移設やインターネット回線の手続き費用などが発生することもあるため、事前に見積もりを取っておく必要があります。
⑤家具・家電の購入費用
新築に合わせて新しい家具や家電を購入する場合の費用です。特に、カーテン、照明器具、エアコンなどは見落とされがちですが、数十万円単位での出費になることが多いため、事前に予算を確保しておくことが必要です。
⑥仮住まい・賃貸費用(建替えの場合)
建替えを行う場合、一時的に住むための仮住まいが必要になることがあります。賃貸住宅の契約費用(敷金・礼金)、家賃、引っ越し費用が発生します。工事期間を考慮し、無駄な出費を抑えるためにスケジュール管理が重要です。
⑦地鎮祭・上棟式の費用(任意)
建築工事の安全を祈願するために行う神事の費用です。
一戸建ての維持にかかる費用

念願の一戸建てを建てた後は、維持するための維持費がかかります。初期費用以外にもどのくらいの費用がかかるのか計算してから、マイホーム作りに取り組みたいものです。維持費は以下の項目に分けられます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 修繕費
- 各種保険料(火災保険・地震保険など)
固定資産税
地方税の一つで、会社や畑、お店などの固定資産を所有する者が毎月国で定められた額を市町村に納める税金のことです。戸建てを購入した後は、所有者が納期ごとに支払う義務が発生します。
仮に2,000万円の戸建てを購入した場合、固定資産評価額は実勢価格の70%程度のため「2,000万円×70%=1,400万円」となり、固定資産税額は「固定資産評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)」と計算することから「1,400万円×1.4%=196,000円」という計算になります。あくまで目安ですので、正確な費用は市区町村から通知される固定資産税の納税通知書を確認してみてください。
都市計画税
都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした税金のことを指しており、原則として市区町村が定めている「市街化区域内」にある土地・建物のみに課税されます。都市計画法で定められている市街化区域は現在増加傾向にあり、国土交通省がまとめている「都市計画現況調査 令和4年調査結果」によると、全国の市街化区域の面積は145万3520ヘクタールと年々増え続けています。
修繕費
戸建てを建てた後、何も手入れをせずにいると外壁が剥がれてしまう事や、雨漏りが発生してしまう恐れがあります。何十年先も安心して暮らすためには、建物の状態を保つための定期的なメンテナンスが欠かせません。老後まで安全に住み続けるためメンテナンスやリフォームにかかる費用も必要になります。
各種保険料(火災保険・地震保険など)
地震などの予期せぬ自然災害や、火事に備えて各種保険料への加入はとても重要です。現在は火災保険と地震保険をセットで契約する方が多くなってきています。保険料は、戸建ての広さや構造、保証期間などによって変わってくるので、契約前に確認することがおすすめです。
新築一戸建てにかかる費用シミュレーション

予算によって、戸建ての外観や内装は変わってきます。予算ごとにどのような家を建てられるのか、費用別の戸建ての特徴について紹介します。
1,000万円台~2,000万円台前半のローコスト住宅の場合
高度な間取りや複雑な設計ではなく、全体的にシンプルな外観と間取りになるでしょう。複雑なデザインにすると使う木材が多くなるので、どうしても材料費や人件費にコストがかかってしまいます。
完全な自由設計とはいきませんが、シンプルだからこそどんな家具やインテリアにも合う空間が作れます。
2,000万円後半~4,000万円台の住宅の場合
2,000万円後半は、建築費の他にも発生するコストの内訳を工夫すれば理想の戸建てにできるでしょう。例として、家の外観や内装はシンプルにして、好みに合わせて家具やキッチン設備をカスタムするなどがあります。
3,000万円からは自分の理想を詰め込んで盛り込みたい条件を叶えられる場合が多いでしょう。家族との暮らしに合わせて戸建ての間取りや設備を工夫し、木材など設計に使う材料にこだわるのもおすすめです。4,000万円台になれば、人気の吹き抜けや無垢材のウッドデッキなども作れて家づくりのバリエーションも増えます。
戸建てを建てる場合は予算計画を綿密に!

マイホームを建てる際には、事前の予算計画をしっかり行うことが重要です。戸建てを建てる際はもちろんですが、建てた後も維持するための費用が必ず発生します。
物件を所有することだけを目的にせず、どのくらいの費用を住宅にかけるか家族としっかり話し合いながら予算計画を組みましょう。想定外の支出にも対応できるように、余裕を持った予算計画で素敵な住まいづくりをしてください。